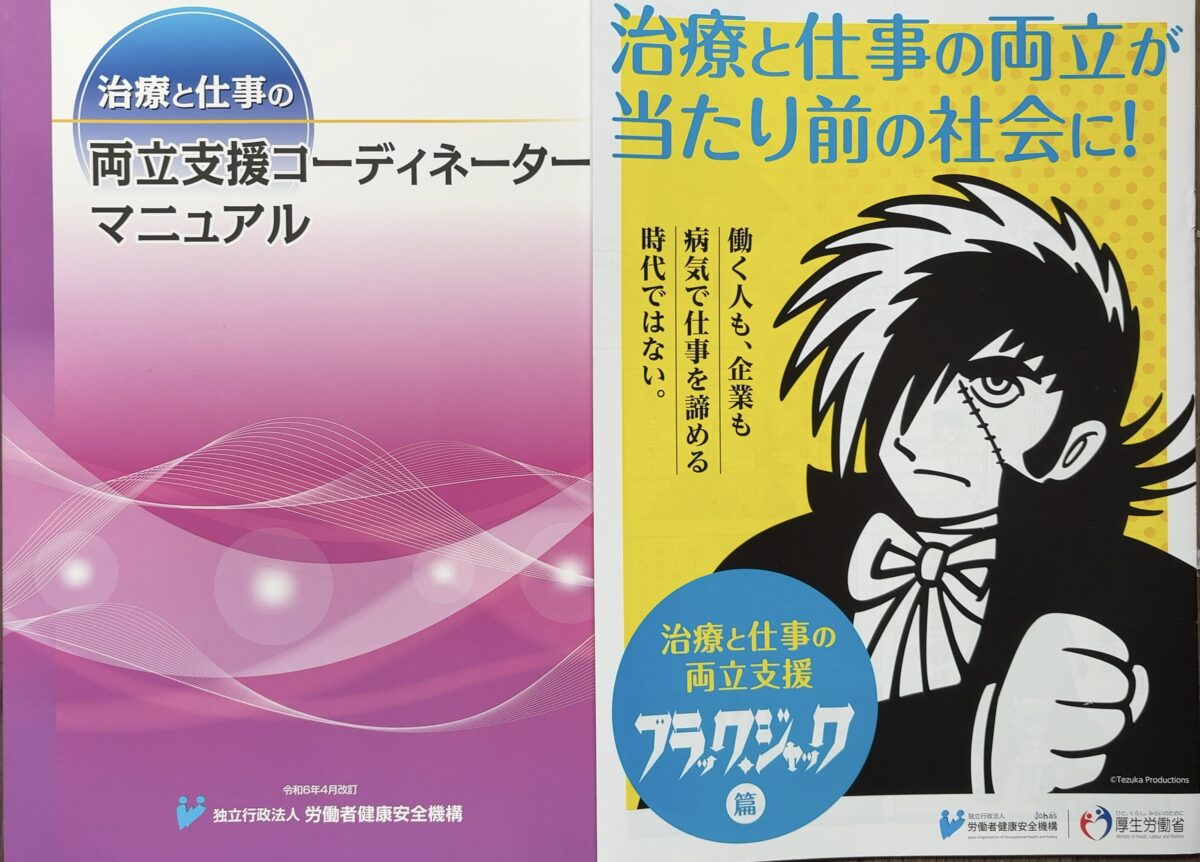ブログをご覧いただきありがとうございます。
今回は、人を活かす経営=人的資本経営を社外に力強くアピールし、優秀な人材の獲得につなげるための具体的なお墨付き(証明書のようなものですね)のお話です。
国や省庁、民間団体が設けている認定制度やシンボルマークのことです。
最近、ある会社さまに合うのはどの認定制度かを調べ始めたところ、ご紹介したい制度がいくつもありました。
限られたリソースで奮闘する中小企業に、こういった認定マークがどう役立つかを一緒に見ていきたいと思います。
もちろん、経営面で負担にならないことが一番ですので、おおよその費用感も明記しています。
なぜ、認定制度の取得が「攻め」の戦略になるのか
少子高齢化が進む日本では、優秀な人材の獲得競争は激化しています。
求職者は転職先を選ぶ際、「働きやすい環境か」「成長できる機会があるか」を非常に慎重に検討しています。
このとき、国や公的な団体が発行する認定マークは、求職者にとって「この会社は安心できる」というお墨付きとなります。
認定マークをホームページや求人情報、名刺などでPRすることは、中小企業にとって以下のような強力なメリットにつながります。
1. 採用競争力が格段に高まる
認定マークは、企業が法令遵守や多様な働き方の推進に真剣に取り組んでいる証です。
特に「くるみん」や「えるぼし」といったマークは、育児層や女性、若手といった特定のターゲット層に対し、安心感と強い訴求力を持っています。
2. 企業のブランドイメージが向上する
ダイバーシティ促進や労務管理の適正化は、現代社会が求める正しい方向性です。
認定マークの取得と開示を通じて、企業は社会的な信頼や価値を獲得し、ブランドイメージを確実に高めることができます。
3. 大企業や公共機関との取引で有利になる可能性
ESG投資(環境・社会・ガバナンスへの配慮)への関心が高まる中、大企業はサプライチェーン全体に対し、取引先である中小企業がどのような社会的価値を提供しているかを重視するようになっています。
認定マークは、その証明の一つとなります。
中小企業が目指したい主要な認定制度
認定制度は多岐にわたりますが、ここでは中小企業の経営者や人事担当者が「うちでもできるかも」と思える、PR効果が高い分野をご紹介します。
働き方の多様性と公平性を証明する
1. 働き方の多様性と公平性を証明する(くるみん、えるぼし、トモニン)
最も求職者への影響力が強いのが、子育て支援や女性活躍、介護支援といった分野です。
• くるみん認定(子育てサポート企業)
厚生労働省による「従業員の子育て支援に積極的に取り組む企業」を認定する制度です。
男性の育児休業取得状況や残業削減状況などが評価されます。
上位認定には「プラチナくるみん」があります。
【費用感】 申請費用はかかりませんが、育休制度の整備や代替要員の確保など、制度を機能させるための内部投資が必要です。
• えるぼし認定(女性活躍推進企業)
厚生労働省による「女性の活躍推進に関する取り組みが優良な企業」を認定する制度です。
採用比率、管理職比率、継続就業状況など5つの評価項目があり、満たす項目数に応じて3段階の認定が受けられます。
さらに上位に「プラチナえるぼし」があります。
【費用感】 申請費用はかかりませんが、女性が管理職として活躍できるキャリアパス構築など、組織体制の見直しや教育への投資が必要となります。
• トモニンマーク(仕事と介護の両立支援)
厚生労働省による「従業員が仕事と介護を両立できる職場環境の整備に努めている企業」に付与するマークです。
介護休暇制度や短時間勤務制度などの取り組みを定め、厚生労働省の「両立支援のひろば」に登録するだけでよく、比較的容易に取得できるのが特徴です。
【費用感】 申請費用はかかりませんが、制度設計と周知徹底にかかる時間的コストが主となります。
健康や安全・育成への姿勢をアピール
2. 健康や安全・育成への姿勢をアピールする(健康経営優良法人、ユースエール)
従業員の安全や健康を大切にする姿勢、若手の育成は、企業への定着率や生産性に直結します。
・安全衛生優良企業認定(ホワイトマーク) 後述のホワイト認定企業とは異なります。
厚生労働省による「労働者の安全や健康を確保するための取り組みを高い水準で維持している企業」を認定する制度です。
【費用感】申請費用はかかりませんが、労働者の健康保持増進対策、メンタルヘルス対策、安全管理など、幅広い分野で積極的な取組が必要になり実施のためには費用がかかります。
• 健康経営優良法人
経済産業省が、地域の健康課題や健康増進の取り組みを積極的に実施している企業を顕彰する制度です。
企業規模に応じて①大規模法人部門と②中小規模法人部門に分かれています。
②中小規模法人部門の上位法人は「ブライト500」の冠が付加されます。
定期健診受診率やストレスチェックの実施状況などが評価されます。
【費用感】
中小規模法人部門認定申請料:15,000円(税込16,500円)/件
大規模法人部門:80,000円(税込88,000円)/件
更新には毎年申請が必要になります。 ※ここは要チェックですね
ストレスチェックの実施や、健康増進施策(外部サービス利用など)には実費が発生します。
• ユースエール認定(若者育成推進企業)
厚生労働省が若者の採用・育成に積極的で、雇用管理の状況が優良な中小企業を認定する制度です。
【費用感】
申請費用はかかりませんが、育成プログラムやOJT体制の構築が必要な場合には時間と費用がかかります。
その他の取り組み
3. コンプライアンス・環境対応等への取り組み(ホワイト、なでしこ、エコ・ファースト等)
• ホワイト企業認定
民間の「日本次世代企業普及機構(ホワイト財団)」が実施する認定制度です。
評価項目はビジネスモデル・生産性、ワーク・ライフバランス、健康経営、ダイバーシティ&インクルージョン、リスクマネジメント、労働法遵守など多岐にわたります。
法令遵守度合いを広く対外的にアピールしたい場合に有効です。
【費用感】
民間の認証制度であるため、申請や審査、コンサルティングに費用が発生します。
難易度は国の認定制度よりやや高めとされています。
• 新・ダイバーシティ経営企業100選
経済産業省による多様な人材(女性、外国人、高齢者など)の活躍を経営成果につなげている企業を称える制度です。
これは認定マークというよりも表彰・選定に近いプログラムで、ダイバーシティ経営そのものに積極的に取り組んでいるというPRになります。
【費用感】
直接の申請費用はかかりませんが、多様な人材が活躍できる組織文化や人事制度の構築、教育などに大きな投資と時間が必要となります。
• エコ・ファーストマーク
環境省による地球温暖化対策やリサイクル対策など、自らが先進的、独自的でかつ業界をリードする環境保全の取り組みを約束した企業に対して、環境省が付与するマークです。
非常に高い水準の取り組みが求められます。
エコ・ファーストマークは難易度が高いですが、環境問題への取り組みはESG投資やSDGsの流れで重要性が増しています。
中小企業でも、例えばサプライチェーンにおけるCO2削減など、自社の事業に合ったSDGs目標を明確化し、その進捗を情報開示するだけでも、企業イメージの向上に繋がります。
• なでしこ銘柄
経済産業省と東京証券取引所が共同で、女性活躍推進に優れた上場企業の中から選定する制度です。
中小企業が直接このマークを取得することはできませんが、希望はあります。
上場企業が目指す最高水準の女性活躍の指標(例:女性管理職比率、育休取得状況)を自社の目標設定の参考とし、達成度を社内で公開することで、社員のモチベーションや対外的な魅力向上につなげることができます。
💡3つのヒント
• 自社に合う認定制度を見つける
「うちが取り組むならこの制度が良いかもしれない」と考えられることがポイントです。
まずは自社に合う認定制度を見つけてイメージしてみましょう。
採用したい層や解決したい課題(例:若手定着、女性管理職育成)を明確にし、最も効果的なマークから一つを選んでいきます。
• 自社の強みを「データ」で見える化する
高度なITツールがなくても、簡易的なサーベイ(調査)やアンケートなどを通じて、「自社の強み」をデータで把握することも重要です。
また従業員との対話の機会を増やしていくと、自社を選んだ理由や今後の業務の展望などからヒントが見つかるかもしれません。
• 国の支援策を積極的に活用する
実際に取り組みを始めようとすると、必要になる評価制度や測定などが出てきます。
例えば、人事評価やエンゲージメント測定のITツール活用は有効ですが費用が課題となります。
中小企業・小規模事業者は、IT導入補助金の制度によりITツール導入費用の1/2以上が補助される可能性があります。
東京都のように従業員エンゲージメント向上に向けた取り組みに対し奨励金を支給する地方自治体の支援策も増えています。
これらの制度を積極的に利用し、費用負担を軽減しながら取り組みが進められるかを確認してみましょう。
次回は、それぞれの制度の特徴などを見ていきます。