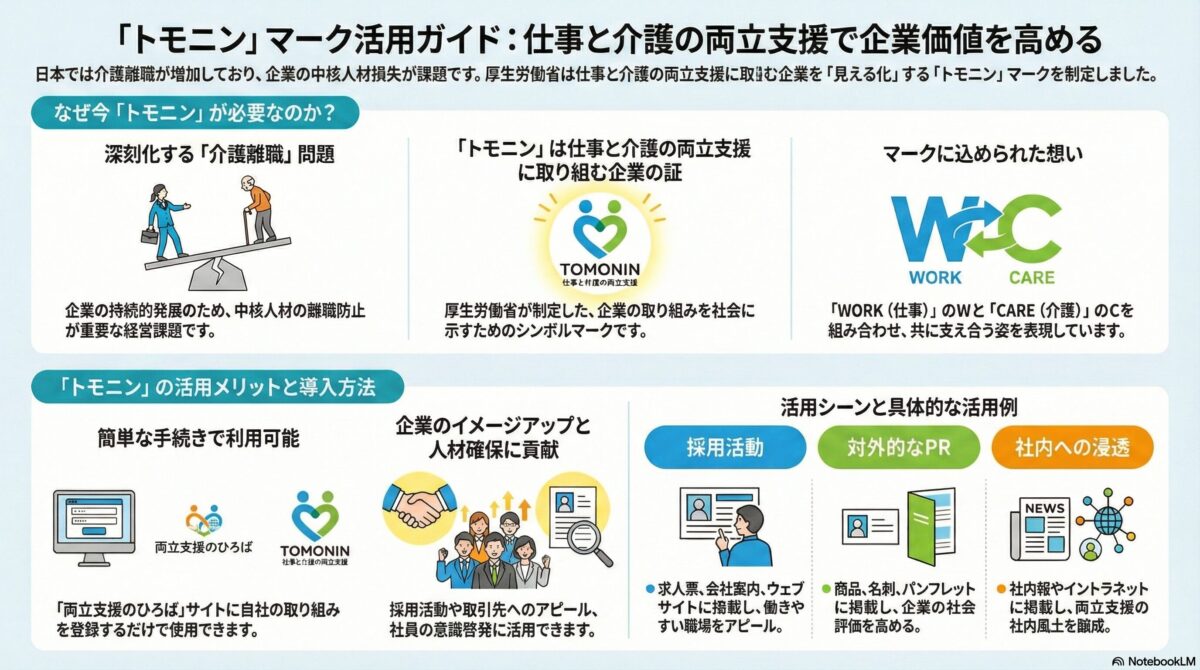先日、厚生労働省による令和7年度 職場のメンタルヘルスシンポジウム
「中小企業におけるメンタルヘルス対策~ストレスチェック義務化への対応~」が開催されました。
労働安全衛生法が改正され(時期としては、2025年5月14日の公布から3年以内に施行される予定)これまで努力義務だった50人未満の事業場にもストレスチェック実施が義務化されます。
タイムリーな話題であり、どのような話が出ているのか気になりますよね。
おおまかな内容を記載してみました。
全部は拝聴できていないため、詳しい資料などは厚生労働省のサイトをご覧ください。
なぜ中小企業こそメンタルヘルス対策が必要なのか
国内で人手不足が叫ばれる中、限られた労働者で安定的に事業を継続するためには、社員の健康を守ることが重要になります。
・不調からの回復の難しさ
一度メンタルヘルス不調に陥ると、元に戻すのが難しく、職場復帰しても約半数が再発するというデータがあります。
・ストレスの多重性
現代社会には出来事ごとのストレスの引き金となるものが多々あり、社員は日々多くのストレスに晒されています。
ストレスチェックは、労働安全衛生法に基づき、社員の「仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスの有無とその内容」を把握し、職場における労働者の安全と健康を確保するための重要な仕組みです。
メンタルヘルスケアの3つの視点
メンタルヘルスケアは、主に次の3つの視点から連携して行われます。
- セルフケア
労働者自身がストレスに気づき、相談すること。
・重要性:人間にはストレスの表示がないため、自分から「ちょっと相談する」という行動が非常に重要です。
相談は、荷物を一度外に出して整理し、不要なものを捨てる「片づけ」のようなものです。
・ゲートキーパー:厚生労働省が示している「ゲートキーパー」の考え方(気づき→声かけ→傾聴→専門家へのつなぎ)が大切です。 - ラインケア
管理監督者(上司)によるケア。
・対策: 仕事の量、質、人間関係に気を配り、不調のサイン(変化)に気づき、声をかけることが重要です。 - 事業場内・事業場外資源によるケア
・産業医、保健師、外部相談窓口などの専門職によるケア。
・産業医の役割: 治療を直接行う主治医とは異なり、「健康に関する相談の場」として機能し、医学的な知見を事業主に助言・意見具申する役割を担います。
事例1:室蘭まちづくり放送株式会社
社員7名、平均年齢42歳という少数精鋭のコミュニティFM局。
多忙な業務(ラジオ放送、営業、イベント運営、YouTube配信など)による、長時間労働や不規則な生活から生じるストレス性疾患を未然に防ぐために取り組んだ事例です。
・課題の認識
労働時間が長く、休みや食事が不規則になり、ストレスが溜まり、メンタルヘルス不調者が発生してしまっている。
○具体的な取り組みと工夫
1.法定ストレスチェックの導入
・健康経営優良法人の認定要件をクリアするため、保険会社のアドバイスを受け、法定ストレス
チェックを導入。
・紙ではなく、メールリンク経由での受験を採用し、匿名性と集計の手間を解消しました。
2.多角的な現状把握
・ストレスチェックに加えて、健康習慣アンケートも実施。
・より詳細な健康課題(運動・睡眠・食事など)を把握しました。
3.柔軟な制度
・少人数ながら、時間単位の有給休暇、対象者への15日のリフレッシュ休暇、テレワークを導入 し、働く時間の柔軟性を高めました。
4.睡眠への投資
・ストレスと睡眠不足の関連性に着目し、オーダーメイド枕を社員に提供し、質の高い睡眠をサ ポートしています。
5.経営者の率先
・経営者自身がストレスチェックを受け、結果を共有し、健康づくりを自ら率先して引っ張る役割を担っています。
○成果
・取り組みの継続により、健康意識が数値として向上し始め、特にストレスチェック後の高ストレス者の相談状況も安定していることが確認されています。
詳細な事例はこちらです→室蘭まちづくり放送株式会社さま
事例2:三重太平洋工業株式会社
セメント原料の採掘・供給を行う従業員76名の企業で、ストレスチェックの結果を経営戦略に組み込み、PDCAを回して改善を実行した事例です。
○具体的な取り組みと工夫
1.産業医による継続的な関与(体制整備)
・従業員50人未満のため、任意で産業医を選任。
・毎月の衛生委員会に産業医が継続的に参加し、個人面接指導や集団分析の結果をもとに改善策を共同で検討しました。
2.改善に直結する調査票の採用(ツールの工夫)
・2020年から「新職業性ストレス簡易調査票(80項目短縮版)」に切り替え。
・これにより、ワークエンゲージメントやハラスメントの観点も測定可能になり、集団分析の結果を具体的な改善施策(例:上司・同僚の支援、職場の物理的環境)に結びつけやすくしました。
3.結果に基づく具体的な職場環境改善
・集団分析で夏の現場の負荷が高いと判明したときには、スポットクーラーの追加設置や空調服の配布といった物理的な改善を実行しました。
4.ラインケア研修の体系化
・ストレスチェックで可視化された「上司・同僚の支援不足」への対策。
・管理職・リーダーを対象に、聞く、伝える、褒める、叱るといった現場で使える行動スキルを体系的に学ぶ研修を実施し、ラインケア力の底上げを図りました。
5.定着につながる制度
・女性専用更衣室・トイレの設置
・入社後3ヶ月間の日報(ノート)による学びと不安の共有(部門長がコメントを返信)により、早期の不安や変化を把握し、定着率の改善につなげました。
○成果
・長時間労働の是正、業務負荷の平準化が進んでいます。
・働きやすさの向上により離職が減り、定着率が改善しています。
・従業員の満足度が高まった結果、リファラル採用(社員からの紹介)が活性化し、優秀な人材の採用につながる好循環が生まれました。
詳細な事例はこちらです→三重太平洋工業株式会社さま
事例3:名四金属株式会社
鉄スクラップ卸売業を営む従業員6名の小規模企業で、世代交代期にメンタルヘルス対策の必要性を痛感し、自ら体制を整えた事例です。
○具体的な取り組みと工夫
1.平和な会社が直面した危機:
・創業以来、待遇も良くフラットで平和な社風だったが、世代交代による新人採用が始まると、世代間の考え方のギャップや人間関係の不満が噴出。
・不満がエスカレートし、役員(社長)が社員の個人的な悩みまで含めてすべてを面談で受け止めざるを得ないサンドバッグのような状態に陥り、役員自身の心の健康が危ぶまれました。
2.法令義務を超えた自主的な対応
・労働基準監督署からの指摘や、高齢ドライバーの健康管理の難しさを痛感した経験から、従業員数にかかわらず産業医と契約。
・外部専門家による相談窓口を設置し、産業医と連携することで、役員が負っていた心の負担を軽減しました。
3.ストレスチェックの実施
・外部相談窓口の機能強化も目的の一つとしてストレスチェックを実施(マークシート方式)。
社員からは「自分の精神状態の確認になった」と好意的な反応が得られた。
4.健康習慣アンケートの活用
・ストレスチェックに加え、健康習慣アンケートを実施。
・アンケートのフィードバックと合わせて外部の健康経営アドバイザーによる健康セミナーをカジュアルな場所(ファミレスなど)で開催しました。
・社員の健康意識向上とコミュニケーションの機会を創り出しています。
○アドバイス
・採用活動を始める前に、「メンタルヘルス対策を考えている会社だ」という姿勢を打ち出すことが、採用ミスマッチを防ぐ上で重要。
・小規模な会社ほど、経営者と社員の距離が近いため、人間関係の問題や個人的な悩みが経営者に集中しやすく、素人(役員)だけでは対応しきれないことがあります。
・「話し合えば分かり合える」という甘い考えは危険であり、メンタルヘルスの専門家による第三者的な介入が、社員だけでなく経営者自身の心の健康を守るためにも必須です。
詳細な事例はこちらです→奥村金属株式会社さま
資料や詳細の事例などは、厚生労働省の職場のメンタルヘルスシンポジウムをご覧ください。